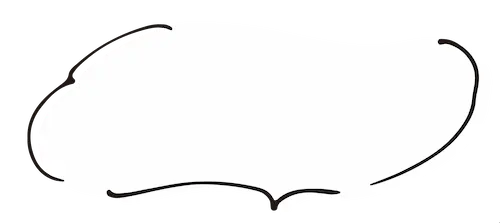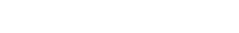【編集長日記vol.2】サンタがワタシにくれたもの

年を重ねるごとに、クリスマスから「初めて」が奪われていった。
「好きな人とのはじめてのクリスマス」
「はじめて行く有名なイルミネーション」
「はじめて予約の取れたクリスマスディナー」
徐々に「初めて」はなくなり、感情が使い古され、いつの間にか「クリスマスだから」という義務感だけが残るようになった。
見飽きたイルミネーションを、棒読みの「はじめて」で彩る。
確かに美味しいけれど、よく分からない名前のついた重いコース料理を、知ったような顔で平然と食べる。
「今年も特別にしようと思ったけど、なんだか違ったな」
サンタなんて信じていないのに、毎年「サンタが来ない」ような気分だった。
楽しかったし、幸せだった。だけど、何故か虚しかった。
それが、どうだ。
子どもが生まれた途端、クリスマスはまた「真新しい存在」になった。
初めてのサンタ、初めてのプレゼント、ケーキ、雪。
我が子の目を通して、「初めて」がまた重なっていく。
色褪せたイルミネーションが、再び煌びやかに光り始めた。
飾られた電球の球を指差しながら、息子が「ホシ」と言った。
驚いたような、輝いた瞳で覚えたての「きらきら星」を歌った。
そうか。君にはあれが「星」に見えるのか。
母ちゃんは忘れていた。あの光があんなに綺麗なものだということを。
混雑する街で、人に揉まれながら、おしゃれな人々をかき分け、母ちゃんの制服姿で必死に隠れてプレゼントを選んだ。
こだわりの料理も、ニュースになるようなイルミネーションもなかったけれど、それでも、人のために生きることが、こんなにも楽しいと、また気づかされた。
息子の車のおもちゃを買うために飛び込んだトイザらス。
目的のおもちゃを見つけた瞬間、私の心は跳ね上がった。
そのおもちゃを渡した時の息子の笑顔を想像すると、もう嬉しくて仕方がなかった。
あの日をこんなに待ち遠しいと感じたのは、いつ以来だろう。
ふと見渡せば、知らない母ちゃんたちが、みんな同じ顔をしていた。
ああ、そうか。
私たちはずっと「いい子」にしてきたから。
だから、一番特別なプレゼントをもらったんだ。
どれだけ苦しくて理不尽な現実に打ちのめされても、扉を開けて、その笑顔があれば全ては吹き飛ぶ。
特別な薬箱、宝石。そんな存在を、私たちは手に入れた。

初めて会った誰かの母ちゃんと、同じトミカのおもちゃの前で目が合い、ふたりで悪戯っぽく笑った。
今年からは、私たちが「サンタ」だ。